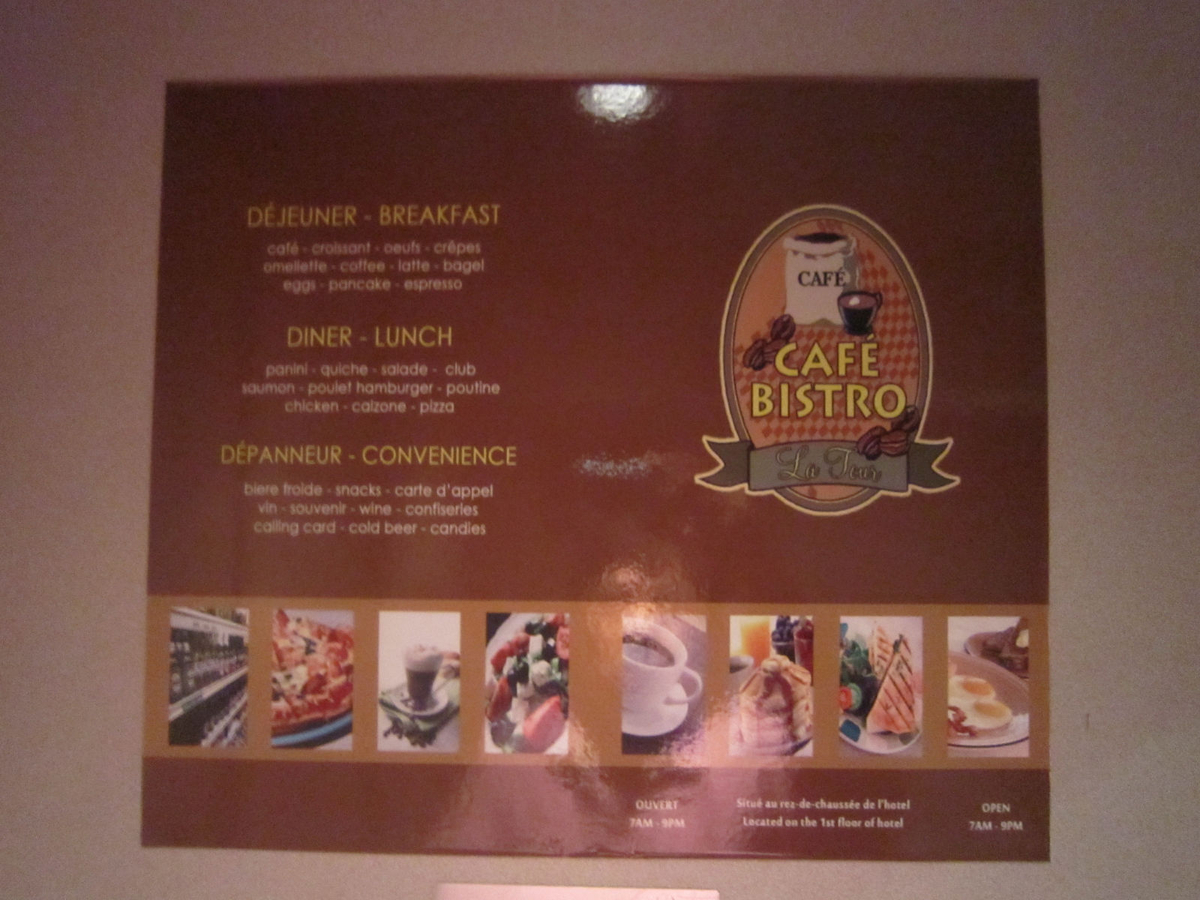ついにグランドオープン。大学職員のランチタイタイムのお笑いネタとしてご活用ください。なお、大阪ローカルを注釈なしのそのまま書きますのでがんばってついてきてください。大学職員の方には新キャンパスを作ったらどうなるかを学ぶ良い機会になると思います。
新キャンパスに何ができるの?
ハム大森ノ宮キャンパス建設の意味合いは二つ。一つは、いくつもあるハム大キャンパスの本部機能を持ちます。そのため、次回の工事(1.5期工事?)では、(いわゆる)理事長さんや学長さんのお部屋も作られます。で、主たる目的は、(いわゆる)すべての学部一年次学生への初年次教育の場となります。ハム大の説明では、中百舌鳥・杉本町キャンパスのようにキャンパスが分散していて、すべての学生が集まれる場が無かったので(筆者には大きく説得力の欠ける説明に感じます…)、初年次教育(いわゆる)ぱんきょ~を行う場として作られたようです。ただし、文学部と生活科学部(一部)と医学部リハビリ学科は、卒業(修了)するまでの間、ここでお勉強することになります。それもなんだか違和感を持ちますが…。
近年、日本の大学で、初年次教育のため、これだけ大規模に新たにキャンパス・建物を作ることもレアですので、大学職員の皆さんがいるそれぞれの大学においても学びになるとも思います。なお、ブログの内容のうち、大学に関する情報は、ハム大HPから得ています。ですので皆さんも筆者同様みることは可能。では進めていきますね。
キャンパスはどこ?
場所は、大阪市城東区。このわかりにくい写真(下)は、筆者がJR環状線の天王寺発➡大阪行きに乗り大阪城公園駅北あたりから撮ったもの。右上にある茶色っぽいの⇩建物が森ノ宮キャンパス。お隣の白いのがURさんが1970年代に建てた高層住宅群。
ここで学ぶ学生への通学区間証明(通学定期の発行)ができる駅は、森ノ宮駅(JR環状線・大阪メトロ)、京橋駅(JR環状線・大阪メトロ・京阪)、鴫野駅(JR学研都市線・大阪メトロ)、緑橋駅(大阪メトロ)と、たくさんあるように見えアクセス豊富そうですがさにあらず。現実的には多くの学生は、森ノ宮駅からの(10分以上)歩きになりそうです。別ルート、特に京橋駅・鴫野駅方面は、(一応)通学推奨道路上に歩道スペースがなく車がビュンビュン行きかう道路。それに、そもそも距離が長いので行くにしても帰るにしても歩くのがだるおもになります。筆者なら強め雨が降っていたら帰宅するかもしれません。なお、直線距離で一番近いJR環状線大阪城公園駅は、安全上の理由で対象外になります。
【写真1】JR大阪城公園駅を大阪方面へ電車が動き出してのすぐの眺め、見てわかるように直線距離でもかなり遠方にあるのがわかります。で、駅とキャンパスの間にはJRとメトロの車庫があるのでダイレクトに歩くことはできません、そのため、将来的には、この駅の北側から歩行デッキを第二寝屋川沿いに作り、大阪メトロ森ノ宮新駅まで結ぶ計画があるよう、、ですが、、JRの線路を回り込んで作らないといけないのでかなりの距離ロス、多分、そして結局、森ノ宮駅~森ノ宮キャンパスまでの距離と大して変わりません。この遠さ、距離感を東京でいうと東西線の大手町駅から京葉線東京駅まで歩いていく感じ。新しいデッキにメリットがあるとすれば、環状線にのる選択肢が森ノ宮駅以外にもう一つふえたことくらい…

この地の歴史を紐解く
まず、『森ノ宮』の由来。多くの人は、普通にどこにでもありそうな名前と感じると思いますが、いやいやそれが…。その由来は、JR森ノ宮駅の近くにある鵲森宮(かささぎもりのみや)神社によります。創建は崇峻天皇二年(589年)!。聖徳太子が唯一自ら創建した神社といわれ、単なる伝承だけでなく、多くの古地図、古文書(日本書紀!)にもこの地に神社があることが書かれているようです。ついでに聖徳太子つながりでいえば四天王寺さんもご近所でお待ちしています。
そして時は流れ、この場所が改めて、歴史上知られるようになったは、石山合戦のあたりから。この地を拠点とした大坂石山本願寺の顕如さんが、織田信長さんの勢力と互角の戦いをした場所。それを横目で見ていた豊臣秀吉さんは、この地が、陸運、水運、海運のハブとなる好立地であるところに目をつけて大坂城を作ります。
大坂の陣~江戸期
冬の陣の際は、南北に流れる平野川の東岸が徳川勢の上杉景勝さんと佐竹義宣さんのポジションとなり布陣。当時は遮るものがなかったので、この地から大坂城の天守閣を眺めることができたと思います。ただ、この場所は、平野川以外にも多くの河川・運河があったので豊臣側にも徳川側にも直接対峙する戦闘には不適な地だったようです。
で、時はもう少し流れ、江戸期には、平野郷や、さらに奈良方面からの物資の運搬に重要な役割を果たしていたようです。そして今では普通の川になりました。
大阪陸軍造兵廠
明治期より置かれた重要な兵器工場。(帝国陸軍最弱と噂された…)大本営直轄大阪第四(淀)師団とともに拡大を続け、昭和初期には大坂城の東側一帯は巨大な陸軍の軍事工場・研究所が立ち並ぶようになりました。
で、そんなところですから、アメリカ軍の空爆の対象となり、昭和20年3月頃から何度も爆撃の試みがありましたが、そのたびに天候等々の幸運があり難を逃れてきました。しかし、終戦前日の8月14日にB29約150機による大規模空襲を受けて完全にがれきの山に。爆撃には焼夷弾ではなく数百発の大型一トン爆弾の集中投下が行われ、そのうち四発が国鉄京橋駅方面に着弾。駅構内に避難していたおびただしい人が亡くなります。一トン爆弾は、当時爆撃機に積載できる最大サイズの爆弾で、その威力はいわゆる着弾地点に大きなクレーターができるレベル。大変お気の毒なことです。また、その時投下された際の一発は、爆発しないまま眠り続け、ハム大新キャンパス造成中に不発弾とし見つかり、その撤去のため、キャンパスのオープンが半年遅れてしまいます。
大阪府立成人病センター、そしてハム大森ノ宮キャンパスへ
そんなこともあり、戦後、この場所は、しばらくがれきの山でしたが、徐々に再開発が始まり、まず、国鉄と地下鉄の車庫となり、そのお隣に大規模な病院建設が行われます。そして昭和34年、この地に本邦初の成人病センターが発足、長年大阪における高度先進医療の中核を担う基幹施設として国から認定され、全国の大学病院、国立がんセンター、国立循環器病センター(当時)と並ぶレベルの医療を提供してきました。しかし時はまた流れ、老朽化等により中央区大手前地区へ移転。名前を大阪国際がんセンターとし高度医療の提供を行っています。そんなで大阪府市が意図するヒガシエリアの拠点には何もなくなったので(使えそうな土地もあるので)大学の誘致をすることになったんだと思います。
そしてそして、長くなりましたが、その跡地がハム大森ノ宮新キャンパスとなります。ハム大は公立大学ですので、大阪府市の都市計画・まちづくりに否が応にも巻き込まれてしまうことを学ぶことができます。
www.soumu.go.jp
新キャンパスへのバーチャルツアー
通学区間は4駅を指定
この4駅の意味とは、(多分)JRさんやメトロさんと相談し、学割定期が発行してもらえる駅の意味。ただし、現実的には、ほぼすべての学生は、JR森ノ宮駅(メトロ森ノ宮駅)を利用します。多分。
そのため、森ノ宮駅から出発するとして、以下のようなルートでご案内。ルートは非常に単純ですが、歩いてみれば以下のことがわかります。それでは、普通に Google Street View 的に見ていきます。(ほんとに)興味のある方はご自身でチェックしてみてください。では、森ノ宮駅(南口)を降りると、まずは東へ!
①阪神高速の高架の下にある中央大通りを東へ歩く。
この通りは、中央分離帯付きの片側2車線道路で歩道も広々し、とても歩きやすい雰囲気。歩く歩道は進行方向左側の道を選択。特に道に迷うことはありません。※早速蛇足ですが、西側へ歩くとすぐ大阪城公園への大きな入口がすぐにあります。いつも素敵ですが、特に桜や紅葉の時期をお楽しみください。
②疎開道路を左へ
この角には、目印となるロイホー(ロイヤルホスト)さんがありますのですぐに認識可。なお、このロイホーさんが、新キャンパス周辺で一番しっかりとしたお食事ができるお店となります。また、もう少し東側にあるメトロ緑橋駅を利用する人も同様にこの角からキャンパス方向に向かいます。
③疎開道路をしばらく歩く
ほんのしばらく歩くと、森ノ宮病院さんという病院が見えてきます。改装後でとてもきれい、この森ノ宮病院さんの付近には、セブンイレブンさんとローソンさんがあり、さらに歩くとデイリーヤマザキさんもあります。で、森ノ宮病院さんあたりから通学方法の規制が厳しくなり、森ノ宮病院さんとUR団地さんの敷地内への立ち入りは禁止、(救急車等の緊急車両がよくくるらしい)特に病院前交差点は横断も(何故か)禁じているので。ここに来るまでに左右どちらかの歩道を決めて歩かないといけません。特に左側歩道を歩いていたら、デイリーヤマザキさんのあるところで横断歩道を渡る必要があります。こんなことでイライラして大学とケンカしても仕方ありませんでの言われたとおりにしましょう…。
で、森ノ宮病院さんからキャンパスまではUR団地が続きます。他には何もありません。ですので、生協以外の食べ物・飲み物をキャンパス内で食べたい・飲みたい場合は、このあたりコンビニ三つで購入する必要があります。※蛇足その2、病院内には売店とおいしそうでお手頃価格な院内食堂がありますが、病院に迷惑がかかるので行っちゃダメです。(特にココは阪大系病院)
④北に向かって歩く歩く!
森ノ宮病院さんより北の景色は進行方向東側にURさんの高層団地が立ち並びます。今現在は、近大さんや関大さんのように駅前に学生向けのいろいろで商売をしている駅前城下町は全くありません。健全と言えば健全。
⑤キャンパス到着!
キャンパスというか敷地内に大きな建物がドカンと一つ、筆者の印象的には大学の建物には見えません。表現するのも難しいのですが、映画館やスポーツ施設が入った巨大構造物のように見えます。今現在の状況を眺めていると、東側敷地に余裕があるように感じるかもしれませんが、このスペースは、1.5期工事という次の建物建設が進むので、広く感じられるのは今だけ。なお、道路を挟んだ西側には、府市の事業で、メトロ新駅と多目的ホール(10,000人収容規模のアリーナらしい)が作られる予定。また、メトロ新駅と、キャンパスを地上二階から結ぶための通路はすでに準備済。
⑤ためしにもっと北方面へ歩くと…
キャンパスを超えると大阪市営中浜下水処理場が見えてきます。見た感じは普通の大きな工場。さらに歩くと第二寝屋川を渡る橋が見えてきて京橋駅へ行くことができます。
筆者の気づき ーJR大阪駅・天王寺駅からキャンパスまで歩きで最低25分は必要ー
ハム大HPによると、主要駅から森ノ宮キャンパスへのアクセスというのがあって大阪・天王寺から約20分としています。それはちゃう!と筆者は疑い深いので調べてみました。
まず、大阪駅・天王寺駅から森ノ宮駅まで10分というのはわかるとして、そこからが謎。所要時間のモノサシを、隣接するUR森之宮第2団地~JR森ノ宮駅までとして計れば、徒歩で約10〜13分、距離にして約800m換算。suumoさん等での、時間表示は、多分団地住宅の位置によってそれぞれ10分~13分と算定していると推測します、、ハム大キャンパスは、UR団地のさらに北側奥にありますのでどう考えても13分以上必要と考えるのが妥当。また電車の待ち時間も入っていませんので、結論的に大阪駅・天王寺駅双方からキャンパスまで20分で行くためには、思いっきりダッシュして走らない限りムリです。
まあハム大さんも『約』は入れてはいますが四捨五入するなら少なくとも25分もしく30分の記載が妥当。筆者に言わせれば、ハム大は、Do not count the number of mackerel roughly. といえます。(意味がわかり、しょ~もな~…と感じる人が一人でもいることに期待します。)※で、筆者は(何気なく)ハム大が時間にこだわるのは何か別の理由・意図がある…と勘ぐっています。それはおいおいにして…。
建物構造が特徴的
見た感じは一棟の大きな十三階建ての建物。十三階建てとした理由は、大阪城天守側から眺める際、建物が生駒山系の稜線を超えないようは配慮したとのこと。四百年の時が過ぎても太閤殿下への敬意がしのばれます。
で、ざっくりの建物の使い分けですが、一階が全ての学生さん関係(食堂・多目的ブース12部屋、音楽演奏可なサウンドスタジオが6部屋etc)、二階は管理部門(事務室etc)、三階~七階が講義関係(教員室+講義室)・ライブラリー(ハム大では図書館のことを『ライブラリー』と呼ぶ)。八階より上は文学部等の学部専門科目の授業が行われる場となり1年次生にとっては別世界。ちなみに面白構造として、エスカレータは、七階まで上り専用で設置。下りどうするかというと、お隣に設置された階段を使うことになります。もはや高齢?の筆者は、単調な下りの階段の方が足がもつれて転倒しそうで怖いです。若い人でも特に雨の日漫然と上り下りしていたら思わぬ事故につながります。十分お気をつけください。なお、エレベータはたくさん設置しているようなので上層階へ行く時にはエレベータをという仕分けをしているんだと思います。
なお、消防法上は、コの字構造になっていて、建物は二ないし三つある形、非常時にはそれぞれの区画の防火・防煙シャッターが下りる仕組みだと思います。(昔、大学の某庶務掛で働いていたころ学んだ記憶があります。間違ってたら御免なさい。)また、建物の構造・性質上、大きな火事の心配はなさげです。あとは津波(南海トラフ)対応あたり?。キャンパスのあるあたりは、海抜3m程度。第二寝屋川・平野川への津波の遡上は十分あり得ます。
そんなで、初年次教育をうける学生さんは、基本的には一階~七階を用いて一年間授業を受けることになります。一年たったら基本的にもう二度と来ることはありません。というか戻ってきちゃダメです。
で、改めて初年次学生向けスペースですが、
一階:食堂・アリーナ・学生厚生施設etc
二階:事務の管理部門
三階:講堂・森ノ宮キャンパス以外の教員のための控室
四階:ライブラリー・教員居室・教室
五階:ライブラリー・教員居室・教室
六階:教員居室・教室
七階:教員居室・教室
ですので、
外見上大きな建物ではあるのですが、以上のいろいろが入っていて思ったほど余裕は(多分)ありません。一階~三階は、授業としては(ほぼ)使用せず、四階・五階もライブラリー(図書館)スペース等が大きく占めているので、多くの初年次学生が学ぶ場所は六階・七階が中心になりそう。
なお、八階~十三階は、使用する用途が異なりますので、実際初年度入学の学生さんの使う範囲はこの建物の半分以下程度となります。
この初年次教育のため、大中小70近い教室を用意しているようですが、固定座席には全員分の電源コンセントを用意しているとのこと。BYOD(Bring Your Own Device)を標榜している大学ですから、やることはやらなきゃなりません。このあたりは(当然ですが)ご立派だと思います。また、車いすスペースもちゃんと用意しているよう。
で、この建物の設計施工は、竹中工務店さん&安井建築設計事務所さんのゴールデンコンビ。HP見ていると京都競馬場(新装)、東京でいえばサントリーホール(リニューアル)なども実績として手掛けるなど超一流。多分、国立大学では、この規模の新造工事をこのような実績ある大手に委ねることはないと思いますので、その意味でも完成度に注目です。
www.yasui-archi.co.jp
キャンパス内情報
森ノ宮キャンパスでは、生協(購買・食堂)さんはチャレンジャー?
筆者が思うに、そもそも、多分当初からの敷地面積、建設計画etcにおいて、学生向けの福利・厚生施設の割合・配分が少なめ?だったのかもしれません。オープンの際のメディアの視線は、無人店舗や食堂リアルタイム混雑予報等に向くと思いますがその実体は…。
①一階食堂は大混雑予想
一階食堂は、約700席を用意。大学の想定では、『6000人の学びの場』としていますので座席が充分なのかがポイント。で、大学・生協は、オープン前から座席数不足を大アピール。そのわかりやすい理由は、他大学の食堂座席配分数と比べ、かなり少な目であることが問題意識を生んでいるんだと思います。また、700座席があっても、学生さんは詰め詰めに座るものでもありまぜん。リュックやカバンはお隣の席におくものです。オトナもみんなやっています。あんまり責めたら可哀そうです。※ご参考までに(とても素敵な)上智大学さんと比較すればその差を感じ取れると思います。
で、そんな混雑の解決策として、科学的な検証を行い、食堂の混雑状況の可視化により、混雑・人流に関するリアルタイムな情報提供を行う予定。要は、各所に人感センサーを置き、いまどこにどれくらい学生がいるかを分析、食堂の混雑予測を行うという画期的・先進的な試みを予定。筆者のようなアナログ人間は、お昼前の授業科目の履修登録者数を曜日ごとに把握していれば、アラートを出すことができてしまうのでは、と考えがちですが、そんなんじゃダメみたいです。ただ、結果的には、大学・生協の予測もおおよそ同じで、午前の授業終了後20分間が混雑のピークと予測。この時間帯を乗り切るため、作るのに時間を要する麺類の販売は一時的に13時まで休止するとのこと(要はお昼時はうどんやラーメンは食べることができない)。筆者個人的には、そこまで予測が出来ているなら人感センサーなんかいらんやんの気持ちになります。また、食堂以外の施策として電子決済(済)の弁当の出張販売も各階で実施する予定で混雑緩和の対処をするようです。
いろいろ学生のみなさま、大変そうですが、みなさんはオトナですから『それやったら最初から食堂をサイズアップしてたらよかったんちゃうん?』なんて思っていても言ってはいけません。
キャッシュレス(現金不要)を前向きに考える
そんなんで、生協としては、忙しい時にレジで現金を渡されるのは面倒なので、生協による nanaco 的な電子決済システムを使ってもらい、レジでの滞留時間の節約に取り組むとのこと。さらに派生型として(日本全国にある大学生協発となるらしい)スマホでオーダーし現物を受け取ることもができるシステム、事前登録していれば、そのままお買い物したらレジを通さず完了となる無人店舗(ウォークスルー型のキャッシュレス無人店舗)もあったり斬新なシステムのショーウィンドウ化も進めています。
なお、筆者としては、ブログの書き込み日が9月23日ですが…そろそろ食堂で何が食べられるか、お値段はどのくらいか教えてあげても良いと思います。(HP上では「主菜・副菜」と「丼・カレー類」のまま時が止まっています。)お忙しいとは思いますが是非ご検討を。
冷たいお水はいつでも!でもお湯は?
キャンパスの食堂では、湯飲み・コップは無くして自費で紙コップを買うようにして現金化されます。SDGsと地球環境のためなら仕方ないことです。その代替措置として、マイボトルを持参すれば給水器からお水をいただくことが可能。お水には、Evian(硬水)やいろはす(軟水)等々様々なタイプがありますが、こちらでは、軟水で高度処理(活性炭やオゾンによる高度浄水処理したもの、いわゆる水道水)を提供。(ただ、一説には)東京の水道水よりおいしく感じられるようです。
で、おいしいお水はとってもありがたいのですが、お湯は?、そんなことは、Don't think, just do. の気持ちにならないといけません。
また、即席系のカップラーメン類については、キャンパスにおけるサスティナブルな循環型社会づくりに取り組む必要がありますので、残渣(残り汁)問題を考慮して、当⾯利用不可。また、当然、UFOあたりも湯切りが必要なので当然(多分)アウト。ただ、飲んで終わりのカップスープ類は別途検討してくれるようです。なんだか、地球環境やSDGsといえばなんでも許される風潮を感じる日々。特に冬場に温かいものなしは身に染みます。
こんな出来事たちにピヨピヨの一年次生たちはどう立ち向かうのか注目です。
omucoop.jp
『知の森』に書籍部(本屋さん)はありません
多分、こちらもスペース上の問題が最大と思いますが、学術書籍を購入できるような購買部はありません。大学関係者以外なら大した話じゃないかもしれませんが、授業や学究のため本に触れ、購入する機会はたくさんあります。Web上での購入も進んでいますが並んでいつ本を物色すらできないことには疑問。また、当初生協は授業用書籍の配布すら行わない(学生の自腹で宅配(数千円)?)ようだったのですが、結局、さすがにそれはあかんやろ!ということになったようで、キャンパス内で購入の電子決済をした2日後にキャンパスの指定箇所でもらえる仕組みにしたようです。ただ、今回はあくまで例外的に教科書購入での便宜が図られましたが、本難民の状態は続きます。
筆者がサジェスチョンするなら、Amazon さんetcでは、かなりの学術専門書籍も購入可能。また、お財布にやさしい中古品もあったりしますので、学生の皆さんトライしてみてください。
⇩隣の芝生で、ない物ねだりしても仕方ありませんが、、上智大学さんは素敵です
www.sophia.ac.jp
ここまでで、文字数9,000カウントに達しましたので、このあたりで一旦区切りとし、後半部分で、教務関係・学生関係+総括と考えてみたいと思います。読んでる方もお疲れ様でした。See you soon.